水質管理について
安全でおいしい水を送るために
安全でおいしい水を供給するために、水質検査は欠かせません。
水源の上流域にある湧水や沢水から家庭の蛇口水に至るまでの水質を最新の機器や方法で、水質基準51項目などについて定期的に水質検査を行っています。
主な検査機器
ICP質量分析装置
水中の鉄やマンガン、亜鉛などの金属成分を分析する装置で、ごく微量の低濃度から高濃度まで測定できます。

イオンクロマトグラフ
水中の塩化物イオンや硝酸態窒素やカルシウム、ナトリウムなどのイオン類を分析する装置で、多くの成分を短時間で測定できます。

ガスクロマトグラフ質量分析装置
水道水などにトリハロメタンや農薬などの成分が含まれていないかを調べる装置で、10億分の1以下の低濃度まで測定できます。

顕微鏡と写真撮影装置
水源やろ過池などに生息する微生物などを調べます。

微生物による水質監視装置及び魚類による監視
水源となる水の水質異常をいち早く検知するため、有害物質に敏感な微生物による水質監視装置を設置するとともに、魚類による監視もあわせて行っています。


水質検査計画
いつでも安全でおいしい水道水を市民の皆さんにお届けするために、毎年、水源から蛇口に至るまでの水質検査について検査地点や項目、回数などを定めた「水質検査計画」を策定し、水道水が水質基準に適合して安全であることの確認はもとより、高い品質を維持するための効率的・効果的な水質管理を行っています。
市民の皆さんに本市の水道水の安全性について、ご理解を深めていただき、安心して快適にご利用いただくため「令和7年度水質検査計画」を公表します。
令和7年度版水質検査計画の概要
|
検査地点 |
水道施設、家庭の蛇口などの定期検査地点(毎日検査34か所、毎月検査および取水井76か所)および その他の検査地点 |
|---|---|
|
延べ検査件数 |
約1,200件 |
|
主な検査内容 |
|
水質検査計画の概要
水質検査計画
水質検査の信頼性について
水道水の安全性は、水質基準への適合性を水質検査により確認することで保証されることから、検査には高い精度と正確性に加え、客観性を兼ね備えた信頼性の確保が不可欠です。
このため、水道部では水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)の規格に沿って水質検査部門に品質管理システムを導入し、この規格の認証を受けています。
これにより、水質検査結果に対する信頼性に新たに客観的要素が加わり、水道水の品質に深く関わる維持管理体制の強化が図られるとともに、本市の水道水に対する皆さんからの信頼性の向上が期待できると考えます。
今後とも、本市の安全・安心な水道水の安定供給に資するよう、水質検査部門における品質管理システムの継続的な改善を図り、一層の信頼性の確保に努めて参ります。
水質検査結果
直近の水質検査結果は次のリンクをご覧ください。
令和6年度水質検査結果の評価
令和6年度に実施した水質検査の結果から、本市の水道水は水源の種類等により水質に特徴があるものの、水質検査結果表に示した水質基準項目51項目全てにおいて基準に適合し、さらには多くの項目で基準値の10分の1以下で、過去の数値と比較しても変動が少なく安定しており、良好な水質と高い安全性を確保しています。
(注)令和7年度の水質検査結果については「令和7年度水質検査結果」よりご確認ください。
浄水場・配水所ごとの水質の特徴
|
横内浄水場 |
水温が四季を通じて低く、pH値は中性でカルシウム・マグネシウム(硬度)も低く、いわゆる軟水といえます。 |
|---|---|
|
堤川浄水場 |
浄水処理に水道用のカルシウム剤を使用しているため、河川の水質の変動に応じて硬度などが多少変動します。 |
|
原別配水所 |
水源が炭酸を多く含みpH値が低いため、空気でかくはんする方法により中性に改善し、硬度は地質の影響で若干高めですが、軟水といえます。 |
|
天田内配水所 |
地下200~400mの深井戸を水源とし、地質の影響でpH値や硬度が若干高めですが、軟水といえます。 |
|
花岡配水場 |
pH値は中性で硬度も低く、軟水といえます。 |
残留塩素
水道水は塩素剤により消毒することが水道法で義務付けられていますが、浄水場などでつくられた水道水が蛇口に届くまでには、相当な時間がかかり残留塩素が消費されるため、水道部ではこの間も十分な消毒効果が保てるよう、蛇口水の残留塩素を0.3~0.5mg/リットルの範囲を目標に管理を徹底しています。
今後も、安全でおいしい水道水をいつでも安心して快適にご利用いただけるよう、水源から蛇口までの水質管理を徹底し、皆さんに信頼される水道システムの運用に努めて参ります。
インフルエンザウィルスに対する水道水の安全性
水道水は、鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどのウィルスに対しても安全・安心です。
鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどのウィルスは、水道水の塩素消毒により感染力が消滅するため、水道水を介して人に感染することはなく、いつでも安心してご利用いただけます。
水道部では、水道水の安全確保に万全を期すため、塩素消毒の適正管理などの衛生上の措置を徹底しています。
有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)への対応について
水道部では、市民の皆さんに本市の水道水を安心してお飲みいただけるよう、令和7年度から、上水道施設及び簡易水道施設での有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質検査を年4回実施しています。
国が示した有機フッ素化合物であるPFOS、PFOAの暫定目標値は1リットル当たり50ナノグラムですが、これまで実施した水質検査では、検出されておりません。
おいしい水の秘密
おいしい水とは?
水を化学的に分析してみると、おいしい水の要件には次の項目があげられます。
|
|
横内浄水場 |
おいしい |
水質基準 |
水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|
|
硬度 (mg/リットル) |
16.6 |
10~100 |
300以下 |
10~100 |
|
蒸発残留物 (mg/リットル) |
62 |
30~200 |
500以下 |
30~200 |
|
遊離炭酸 (mg/リットル) |
2.4 |
3~30 |
- |
20以下 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/リットル) |
1.2 |
3以下 |
- |
3以下 |
|
臭気強度 |
1未満 |
3以下 |
異常でない |
3以下 |
|
残留塩素 (mg/リットル) |
0.6 |
0.4以下 |
0.1以上 |
1以下 |
|
水温 (℃) |
最高17.4℃ |
最高20℃以下 |
- |
- |
注1:おいしい水の要件を全て満たしていなければおいしくないということではなく、バランスがよければおいしく感じます。
注2:厚生労働省令による。
注3:検査方法は臭気によるものである。
注4:水質基準ではないが、水道法で規定されている数値。

- 硬度
カルシウムとマグネシウム量の合計のことで、硬度の高い水(硬水)は、しつこい味がし、反対に硬度が低いと、淡白でコクのない水となります。
(10~100mg/リットルが適) - 蒸発残留物
水1リットルを蒸発させた後の残留物(カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどの鉱物イオン)で、これが多すぎると渋かったり、苦くなる半面、全くないと、味も素っ気もない水となります。
(30~200mg/リットルが適) - 遊離炭酸
水にさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強くなります。
(3~30mg/リットルが適) - 過マンガン酸カリウム消費量
水中の有機物量を示す値です。有機物の多い水は、渋みの解消や消毒のために大量の塩素を必要とするので、水の味は劣ることになります。
(3mg/リットル以下が適) - 臭気強度
水源の状況によりさまざまな臭いがつくと不快な味がします。
(3以下が適) - 残留塩素
水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくします。
(0.4mg/リットル以下が適) - 水温
夏に水温が高くなると、あまりおいしくないと感じられます。冷やすことによりおいしく飲めます。
(最高20℃以下が適)

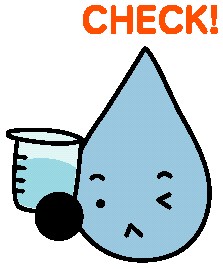
外観
「水道法」では、水道水の外観は無色透明であることとされています。この外観要件の具体的な項目の一つに、「色度5度以下」、「濁度2度以下」であることと定められています。色度及び濁度が水質基準を超えるようになると、色や濁りが肉眼でも分かるようになります。
色度とは
水の色(黄褐色)の程度を人工的な標準色度と比較して数値で表したものです。
自然界における水の着色の主な原因は、樹木や植物の色素成分が水に溶け出したもので、浄水場の処理で取り除きますので、通常水道水にはほとんど色がありません。しかし、建物内の配管の鉄錆などにより赤褐色の色がつくことがあります。このような現象が確認された場合は、少し流して色がなくなってから使用してください。

色の比較
左・・・水質基準適合の水
右・・・水質基準不適合の水
※写真でも違いが分かるように、色を少し強調しています。
濁度とは
水の濁りの程度を人工的な濁りと比較して数値で表したものです。
河川水の濁りの原因は、主に粘土性物質などによるもので、浄水場のろ過で除きますので、通常水道水に濁りはありません。しかし、配管の鉄錆などにより濁り水が出ることがあります。このような現象が確認された場合は、少し流して濁りがなくなってから使用してください。

濁りの比較
左・・・水質基準適合の水
右・・・水質基準不適合の水
※写真でも違いが分かるように、濁度を少し強調しています。
味と臭い
水道水の安全性・快適性を保つために、「水道法」で51項目におよぶ水質基準が定められています。
このうち、水道水の味と臭いについては、「味」・「臭気」として基準が定められ、どちらも「異常でないこと」とされています。
また、水の味や臭いに影響を与える項目についても、基準値が定められています。
水の味や臭いの種類及び強さの感じ方には、大きな個人差がありますが、水道水の異常な味と臭気は、快適な利用の妨げになります。
味
- 水に溶けている物質の種類や濃度によって、水の味を感じます。
- 水の味は、地質、海水などの混入、配管の腐食などによることもあります。
- 通常と異なる水の味は、「すっぱい」、「しょっぱい」、「甘い」、「苦い」、「渋い」などがあります。
臭気
- 水源の状況などによって、水に種々の臭いがつくことがあります。
- 水の臭気は、水源で植物プランクトン(藻類)など生物の繁殖、地質、配管内面塗装剤などによることもあります。
- 臭気の種類は、芳香性臭気(メロン臭など)、植物性臭気(藻臭など)、土臭・カビ臭、生ぐさ臭・魚臭、薬品性臭気、金気臭、腐敗性臭気などがあります。
青森市の水道水の味と臭気は「異常でない」ことを確認しており、味や臭いに影響を与える項目(ナトリウム等)についても、全て水質基準値をクリアしています。
関連リンク
放射性物質の測定について
平成24年1月から、本市独自の検査として水道水の放射性物質の測定を毎月1回行ってまいりましたが、5年間にわたり、放射性物質の検出事例はありませんでした。
このことから、平成29年4月からは、横内浄水場が採水箇所となっており、昭和49年度から青森県が原子力規制庁の委託により実施している環境放射能水準調査の測定結果に基づき、水道水の安全性を確認してまいります。
水道水の放射性物質検査について
平成28年度までの測定結果は次のリンクをご覧ください。
-
平成28年度 (PDF 43.9KB)

-
平成27年度 (PDF 43.7KB)

-
平成26年度 (PDF 43.7KB)

-
平成25年度 (PDF 43.8KB)

-
平成24年度 (PDF 43.7KB)

-
平成23年度 (PDF 40.5KB)

浄水処理発生土の放射性物質検査について
平成28年度までの結果は次のリンクをご覧ください。
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部横内浄水課
〒030-0132 青森市大字横内字桜峰16-3
電話:017-738-6507 ファックス:017-738-9677
お問合せは専用フォームをご利用ください。
