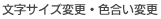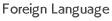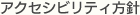ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる新しい医療制度で、75歳(一定の障がいがあると認定されたかたは65歳)以上のかたを対象に、平成20年4月から始まりました。
運営主体は、県内の40市町村全てが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の決定や医療の給付などを行います。
また、市町村では、保険料の徴収や申請・届け出の受付、保険証の引渡しなどを行います。
対象者(被保険者)
広域連合の区域内に住む、75歳以上のかた及び65歳以上で一定の障がいのあるかたが対象となります。
対象となるときは、75歳の誕生日または65歳以上のかたが障がいの認定を受けた日からとなります。
対象者には、1人に1枚の保険証が交付されるとともに、保険料は被保険者全員が納めることになります。
医療費の窓口負担割合
医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、後期高齢者医療被保険者本人や同じ世帯のかたの前年(1~7月は前々年)の所得・収入により、「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
・窓口負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
・世帯構成の変更や所得の更正により、随時再判定を行うため、割合が途中または遡って変更になることがあります。
医療費の窓口負担割合判定については、下記チャートをご覧ください。
国保医療年金課 国保資格チーム 電話番号:017-734-5493
浪岡振興部健康福祉課 国保年金チーム 電話番号:0172-62-1153
窓口負担が2割となるかたには負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)、窓口負担が2割となるかたについては、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。高額療養費の支給対象となるかたには、青森県後期高齢者医療広域連合から口座登録の申請書を郵送します。
詳細については、窓口負担割合が2割となるかたには負担を抑える配慮措置があります(PDF:387KB)をご参照ください。
ご注意ください!
◆厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
◆ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
◆不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)、または消費生活センター(188(いやや!))にお問合せください。
青森県後期高齢者医療広域連合 電話番号:017-721-3821
国保医療年金課 国保資格チーム 電話番号:017-734-5493(窓口負担 担当)
国保医療年金課 国保給付チーム 電話番号:017-734-5343(配慮措置 担当)
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム電話番号:0172-62-1153(窓口負担・配慮措置 担当)
高額療養費制度
後期高齢者医療制度に加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に下表の自己負担限度額を超えて自己負担額を支払った場合は、超えた分が支給されます。
自己負担限度額
〈平成30年8月1日~〉
|
区分 |
外来 |
入院及び世帯ごとの限度額 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3. |
252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%] |
|
| 現役並み所得者2. |
167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%] |
|
| 現役並み所得者1. |
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] |
|
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2. |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1. |
8,000円 |
15,000円 |
現役並み所得者3.・・・住民税の課税所得が690万円以上のかた
現役並み所得者2.・・・住民税の課税所得が380万円以上のかた
現役並み所得者1.・・・住民税の課税所得が145万円以上のかた
一般・・・・・・・・・住民税の課税所得が145万円未満のかた
低所得者2.・・・・・・住民税非課税世帯で、低所得者1.以外のかた
低所得者1.・・・・・・住民税非課税世帯のかたで、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下)
多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合
年間上限144,000円・・・8月~翌年7月の外来の自己負担合計額が上限を超えた場合、超えた金額が支給されます。高額療養費の口座を国保医療年金課に届け出済みの場合は、申請は不要です。届け出をされていないかたについては、青森県後期高齢者医療広域連合より申請書類を郵送します。申請書類が届いた際は、駅前庁舎国保医療年金課の窓口にて、申請をしてください。振込が決定した際は「決定通知書」を送付します。
高額療養費の算定方法
1.75歳以上(一定の障がいがあるかたは65歳以上)の被保険者の外来の自己負担額を個人で合算し、個人単位の自己負担限度額を超える額
2.75歳以上(一定の障がいがあるかたは65歳以上)の被保険者の自己負担額(個人単位の自己負担額および入院の自己負担額)を世帯で合算し、世帯単位の自己負担限度額を超える額
※診療が月をまたがった場合は、それぞれ各月ごとでの計算となります。
※高額療養費の自己負担額には、食事代、病衣代、室料等は含みません。
高額療養費の申請方法
医療費の還付金が発生した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合より「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。駅前庁舎 国保医療年金課の窓口にて、一度申請していただくと、その後は診療を受けた月から、通常4か月後に指定の口座に自動振込となります。振込が決定した際は「決定通知書」を送付します。
(申請窓口)
駅前庁舎国保医療年金課13番窓口
(申請に必要なもの)
・高額療養費の支給申請のお知らせ
・後期高齢者医療被保険者証
・加入者本人の通帳
・加入者本人の印鑑(認め印)
・加入者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
※加入者本人以外への振込を希望する場合は、委任状が必要です。代理人の印鑑(認め印)および代理人の通帳をご用意ください。
入院や外来等で高額な保険診療を受ける場合は「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください
医療機関の窓口に「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院および外来療養、保険調剤、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。(食事代、病衣代、室料等は別途支払いが必要です。)「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請をした月の1日から有効のものが交付されます。
※柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は対象外です。
※区分「一般」、「現役並み所得者3.」のかたは認定証の交付の手続が必要ありません。後期高齢者医療被保険者証を医療機関に提示するだけで、医療費の請求が自己負担限度額までとなります。
(申請窓口)
駅前庁舎国保医療年金課12番窓口
(申請に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・加入者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
※転入したかたは転入前の市区町村の所得課税証明書が必要です。
※「低所得者2.」の該当となるかたで、過去1年間に91日以上の入院があった場合は、入院日数がわかる領収書、請求書などをご提出ください。長期入院の認定は、申請月の翌月1日からとなります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額を超え、かつ支給基準額である500円を上回った場合、支給対象となります。対象となるかたには、青森県後期高齢者医療広域連合からお知らせが送付されます。
高額医療・介護合算療養費の限度額
|
区分 |
後期高齢者医療制度の限度額【年額】 |
|---|---|
| 現役並み所得者3. | 212万円 |
| 現役並み所得者2. | 141万円 |
| 現役並み所得者1. | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2. | 31万円 |
| 低所得者1. | 19万円 |
国保医療年金課 国保給付チーム電話番号:017-734-5343
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム電話番号:0172-62-1153
保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料は、青森県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに定める保険料率(均等割額、所得割率)をもとに計算されますが、団塊の世代が75歳になり始めることによる医療費の増加や現役世代人口の減少が見込まれること、子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組が導入されることに伴い、令和6年度からの保険料率を引き上げることとなりました。
| 均等割額 | 所得割率 | |
|---|---|---|
| 平成31年度まで | 40,514円 | 7.41% |
| 令和3年度まで | 44,400円 | 8.30% |
| 令和5年度まで | 8.80% | |
| 令和6年度から | 46,800円 | 9.90%(※) |
※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えないかたについては、令和6年度の所得割率が「9.20%」になります。
保険料の計算式
均等割額 + 所得割額(※)= 年間保険料
※ 前年中の所得 − 43万円 × 所得割率
後期高齢者医療保険料の軽減措置
被用者保険の被扶養者であったかたの特例
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割額の負担はなく、均等割額は加入から2年間軽減されます。
※元被扶養者であっても、世帯の所得が低いかたは、より高い軽減(7割軽減)が受けられます。
| 所得割額 | 均等割額 | 保険料(年額) | |
|---|---|---|---|
| 平成31年度まで | 負担なし | 5割軽減 | 20,200円 |
| 令和5年度まで | 負担なし | 5割軽減 | 22,200円 |
| 令和6年度から | 負担なし | 5割軽減 | 23,400円 |
均等割額の軽減
被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得で判定します。
満65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した金額に公的年金以外の所得金額を加算した金額で判定されます。
令和6年度より下記の表が適用されることとなりました。
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×[給与所得者等(※)の数−1]以下 | 7割 |
| 43万円+(29.5万円×被保険者の数)+10万円×[給与所得者等(※)の数−1]以下 | 5割 |
| 43万円+(54.5万円×被保険者の数)+10万円×[給与所得者等(※)の数−1]以下 | 2割 |
給与所得者等・・・一定の給与所得と一定の公的年金等の支給を受けるかた
●一定の給与所得者
給与等収入金額が55万円を超えるかた
●一定の公的年金等の支給を受けるかた
(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超えるかた
(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超えるかた
賦課限度額
一人ひとりの保険料額には賦課限度額(上限額)が設けられています。
賦課限度額は、所得の高いかたには応分の負担をお願いし、中間的な所得のかたの負担ができるだけ抑えられるようにするという考え方のもと、
令和6年度から年額80万円に設定されています。
| 賦課限度額 | |
|---|---|
| 平成31年度まで | 62万円 |
| 令和3年度まで | 64万円 |
| 令和5年度まで | 66万円 |
| 令和6年度から | 80万円(※) |
※令和6年度中に75歳に到達して新たに被保険者となるかたを除き、賦課限度額を段階的に引き上げます。
(令和6年度:73万円 令和7年度:80万円)
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料は、以下の要件に該当する場合、高齢者の医療の確保に関する法律第百十条の規定により、原則年金天引き(特別徴収)となりますが、手続により、口座振替での支払いも可能です。
1.年額18万円以上の年金(介護保険料が天引きされている年金)を受給しているかた
2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金天引き対象年金の2分の1を超えないかた
※年金天引きが開始されるまでの保険料は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
後期高齢者医療保険料の支払方法を年金天引きから口座振替に変更する手続
特別徴収(年金からの天引き)の対象者で、口座振替を希望するかたは、下記の【手続1.】及び【手続2.】により特別徴収を口座振替に変更することができます。
【手続1.】 口座振替の登録
提 出 書 類:口座振替依頼書(提出先に備え付けてあります)
必要なもの:1. 振替口座の預貯金通帳、2. 通帳届出印、3.後期高齢者医療保険料額決定通知書または納入通知書
提出先:金融機関または市役所窓口(駅前庁舎 納税支援課、浪岡庁舎 納税支援課、各支所等)
【手続2.】納付方法変更の申し出
提出書類:後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(提出先に備え付けてあります)
※ページ下の関連リンクからもダウンロードできます。
必要なもの:1. 口座振替依頼書の控え、2. 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、いき・粋乗車証等)
提出先:市役所窓口(駅前庁舎 国保医療年金課、浪岡庁舎 健康福祉課)
所得税及び個人住民税の社会保険料控除
保険料の徴収方法を変更することによって、世帯の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合があります。
- 口座振替により支払った場合は、社会保険料控除は保険料を支払ったかたに適用されます。
- 特別徴収により年金から支払った場合は、社会保険料控除はその年金の受給者に適用されます。
保険料の減免
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免が認められることがありますので、ご相談ください。
国保医療年金課 国保税チーム電話番号:017-734-5340
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム電話番号:0172-62-1153
保険料の滞納
特別な理由がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。
また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい、資格証明書が交付される場合があります。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは、全額自己負担となります。
保険料の納付相談
後期高齢者医療保険料の納付が困難なかたのために、納付相談を実施していますので、お気軽にお問合せください。
納税支援課電話:017-734-5209
浪岡振興部納税支援課電話:0172-62-1141
関連リンク
更新情報
2024年4月1日、後期高齢者医療保険料について更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。