
町史研究余録(2)
〜羽州街道と浪岡〜
下十川バス停留所の近くに、「羽州街道」の碑があります。去年、青森県歴史の道整備促進協議会が建立したものです。
羽州街道は山形・秋田まわりの幹線道路で、津軽から江戸に行くとき通った街道です。奥州街道の宿駅
むかしの矢立峠は、相乗温泉の横を通らず、今の矢立温泉付近から峠を上り、湯ノ沢温泉の手前、見返橋付近におりていました。
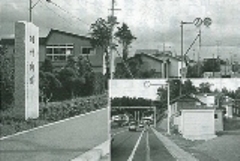 |
| 左:羽州街道の碑(下十川) 右:大釈迦側旧道(杉ノ沢) |
浪岡町内は、ほぼ国道と同じですが、下十川や浪岡、杉沢、大釈迦などでは、道路の改良やバイパスの開通により、旧道は村内で静かに余生を送っています。
江戸時代末期に書かれた「津軽道中譚」は、浪岡について「4つの道が集まる追分の大駅で、往来は格別に賑やかだ。泊まり客で旅籠は繁盛している。」旨を記しています。今の茶屋町あたりの風景でしょうか。
大釈迦峠は羽州街道最後の難所でした。杉ノ沢の信号機の先を右に登る坂が旧道で、道筋は今も山間にその姿を横たえています。鶴ヶ坂側には明治天皇ご巡幸の記念碑があります。
街道は新城の火の見櫓の下を通り油川に達し、奥州街道と再会します。旅人は三厩へ、松前へ、そして青森へと向かったのです。新城と青森が直通で結ばれたのは、明治初期のことです。江戸時代の街道を歩き、記念碑や石仏に触れるのも楽しいことと思います。
なお、大釈迦側の旧道は整備されていませんから、通行には注意してください。
【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】
『広報なみおか』平成7年(1995)8月1日号に掲載
 |