
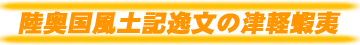
「風土記」とは、奈良時代に朝廷が諸国に命じて提出させた各国の地名・特産物などの報告書である。もとはすべての国々で作成されたと考えられるが、現存するのは、常陸国(・出雲国(などわずか五か国のみであって、陸奥国(は残されていない。ただし、不幸中の幸いと言うべきか、江戸時代に別の書物にその中の記事が部分的に引用されていたことが発見され、今に伝えられている。そこでその内容の一部をここで紹介したい。原文は漢文であるが、紙面の都合上、現代語で要約する。
「八槻(という地名は、ヤマトタケルが東夷(を征討してやって来た時に、賊を射(た矢が落ちたことから名づけられたのである。古老の話では、昔ここに八人の土蜘蛛((先住民)がいたが、景行(天皇朝にヤマトタケルが征討にやって来た。土蜘蛛は力を合わせ、また津軽蝦夷(にも助けを求めて懸命に防御した。しかしヤマトタケルの放った矢により蝦夷は退却し、土蜘蛛は射殺された。土蜘蛛を射た矢は芽吹いて槻の木となり、八槻郷(と呼ばれるようになったという。」
八槻とは、現在の福島県東白川郡棚倉町(八槻のことと考えられる。この陸奥国風土記逸文に記されるヤマトタケル征討説話を史実とみなすことは到底できないが、かといって中央からやって来た国司(がでっちあげた話と決めつけるのも妥当ではないであろう。津軽蝦夷は「日本書紀」にもその名が見え、七世紀の斉明(天皇朝以前から中央政府と接触があり、大和から見て最も遠方に住む有力な蝦夷集団と考えられていたことが知られる。今回紹介した陸奥国風土記逸文を合わせ考えると、単に朝廷だけでなく、陸奥国中においても津軽蝦夷の名が(恐らくその勇猛さから)知れ渡っていたのではなかろうか。
【古代部会執筆編集員 小倉慈司】
※『広報あおもり』2001年5月1日号に掲載
|

