
ふるさとの写真を読む(11)
明治時代も後半になると、新聞の写真掲載は多くなったようです。『東奥日報』の紙面には、日露戦争に関連した写真が目立ちます。
日露戦争は、明治37年(1904)から翌年にかけて戦われました。その規模は10年前の日清戦争に比べて大きく、悲惨なものでした。弘前の8師団も出征、明治38年1月下旬の黒溝台の戦いで主役を勤めました。黒溝台は中国東北部(満州)にあります。激しい戦いは多くの命を奪いました。『東奥日報』は、戦果とともに死傷者の写真を掲載しています。おそらく渡満前に軍で撮影したものでしょう。紙面の保存状況のよい、浪岡町出身の兵士の写真を集めてみました。皆さんの御先祖がおいででしたら編さん室にお知らせ下さい。
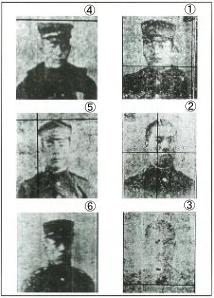 |
| 『東奥日報』明治38年所載 |
①出町嘉之歩兵一等卒。銀出身。野戦歩兵を志願 し、黒溝台で戦死。 ②小笠原由太郎歩兵一等卒。銀出身。黒溝台の戦 いで足部を弾丸が貫通して負傷。 ③山田直一郎歩兵上等兵。五本松出身。黒溝台で 頭部貫通により戦死。 ④平井喜逸歩兵伍長。浪岡出身。黒溝台の激戦を 戦いぬき、3月8日奉天の会戦で下腹部貫通により 戦死。 ⑤古川佐吉上等兵。浪岡出身。奉天の会戦に参加 して戦死。 ⑥中村武治砲兵上等兵。本郷出身。黒溝台で重傷、 戦死。 ⑦野呂丑丈歩兵一等兵。大釈迦出身。戦死。 (写真なし)
戦死した兵士の遺骨は弘前に送られ、分骨式のあと、無言の帰宅をしました。長勝寺(弘前)で各宗派合同の儀式を行ったという記事もあります。
帰国した負傷者は、弘前予備病院、浅虫と碇ヶ関の療養所に収容されました。その数は1,000人を超えています。
新聞が積極的に顔写真や遺族の談話を掲載したのは、写真印刷の技術の進歩のほか、軍部の戦争対策によるものと考えられます。明治10年代の論説中心の新聞は、報道を重視するようになりました。国民の関心も深かったのです。
明治38年9月に入ると各地で戦勝祝賀会が開かれ、村には凱旋者が姿を現わしました。お国のためとはいえ、遺族の気持はいかばかりだったでしょうか。
【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】
『広報なみおか』平成10年(1998)12月1日号に掲載
 |