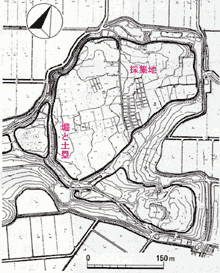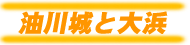
津軽藩の記録によると、天正13年(1585年)に油川城は為信の攻撃によって落城し、城主奥瀬氏は田名部方面へ逃れたとある。しかしながら、油川城に関しては、どのような建造物があり、どのような生活が営まれていたのかというような記録は全くない。そこで考古学の登場である。
現在、油川城の周辺は畑地と植栽地になっており、注意して見ると堀跡や土塁の痕跡が明瞭に残っている。特に、油川や西田沢の市街地を望む丘陵の先端部から、西側にある堀跡までの平場(曲輪()では、畑の畝(から陶磁器などが採集できる。
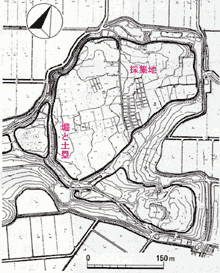 |
| ▲油川城と遺物の採集地(西田沢字浜田) |
その内容をみると、中国製の青磁(・白磁(・染付(といわれる陶磁器、日本産の瀬戸美濃(・越前(などの陶磁器、朝鮮で作られた陶磁器があり、茶臼(、鉄鍋や鉄釘、坩堝(といわれる鋳銅の用具、銭貨や銅製の金具類、そして棹秤(の錘(など多様な生活用具が発見されている。
年代的には15〜16世紀のものがほとんどで、同時期の城館である浪岡城ときわめて類似した状況にある。
一般的に、津軽地域に入る物資の荷揚げ港は十三湊(と考えがちであるが、15世紀末〜16世紀の陶磁器は、十三湊からほとんど出土しない。そのため、この時期の主要な港の筆頭候補として、「大濱」つまり油川の地を想定できるのである。その根拠として考えられるのが、陶磁器を中心とする遺物群である。またこれらの遺物群は、海上交易の盛んな様子をも示している。
海上交通を中心に発展してきた、現在の青森市のルーツを考えるとき、中世後期における油川城・大浜湊の存在は、ますます重要となってくるだろう。
【考古部会執筆編集員 工藤清泰】
※『広報あおもり』1999年3月15日号に掲載
|