
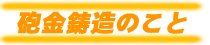
以前はたいていの家で炉を使っていて、そこでは炭を燃料としていた。そして『鉤の華(』と言った炉鉤(が天井から吊(り下げられて、それに鉄瓶を下げて湯を沸かしていた。炉には炉金を埋め、その周りには「油石」と言った「メノウ石」を敷いていたが、その石の多くは、今別の袰月海岸(古くは舎利浜と言った)産のものが使用されていた。
| ▼鉤の華 |
 |
| ▲(財)稽古館蔵 |
ところで、その『鉤の華』であるが、青森では鉄製のものよりも“砲金(青銅の一種で銅と錫(の合金)”製のものが多く使われていた。砲金は錆(にくいことから主に船の金物として使われていた鋳物(製品で、港町の青森では早くから造船業も盛んであったため、砲金製の金具の製造も行われていた。その中でも、茶屋町にある近藤鋳造所は古く、その後に同じ茶屋町に飯田鋳造所ができた。
ある年に、人間国宝の故浜田庄司さんが蔦温泉に宿泊したことがあったが、その際帳場の炉に吊っていた『鉤の華』の素晴らしさに、「それを買い求めたいので紹介してほしい」と主人に依頼した。ところが注文した品がなかなか完成しない。それから3年後、蔦温泉を訪れた際に聞きただしたところ、主人が言うには「考えてみると注文した先が悪かった。何しろ製造している人の名がコンドウ・フクゾウ(近藤福蔵)という人なので、何度催促してもコンド・フクゾウ(今度ふくぞう)と言うだけで、今になってしまった」・・・ということだった。当時は、鋳物を造ることを「ふく」と言ったのにかけてのことで、大笑いしたことであった。
【民俗部会調査協力員 三上強二】
※『広報あおもり』1998年1月1日号に掲載
|

